Megribaメンターインタビュー vol.2 常川朋之さん
【Megribaメンターに聞いてみよう!vol.2】
“ビジネスアイディアの見つけ方と育て方、地域性ってどう活かす?”
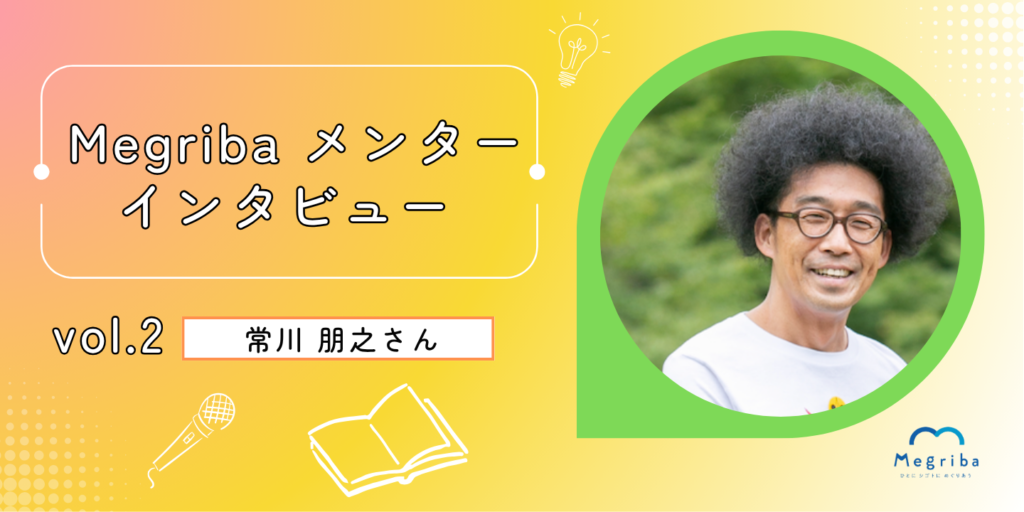
今回は起業アイディアから大手企業の社内新規事業、食品業界から宇宙分野まで、内容や規模感を問わず首都圏を中心に全国で様々な事業支援に携わる常川朋之氏にインタビュー!
ビジネスアイディアの見つけ方やその育て方、また、地域性を活かし方についてお話しを聞いてみたいと思います!
 常川さん、本日はよろしくお願いします!早速ですが、何か新しい事業を始めたいと思った時、ビジネスアイディアはどのような視点で見つけるのが良いですか?
常川さん、本日はよろしくお願いします!早速ですが、何か新しい事業を始めたいと思った時、ビジネスアイディアはどのような視点で見つけるのが良いですか?
 まずは自分の興味関心のあることを知ることが第一歩だと思います。事業の成功は時間の積み重ねでしかなく、アスリートにとっては練習時間が結果に比例するようなものです。なので飽きずに続けられること、人より苦労と感じずに続けられることが大切だと思います。
まずは自分の興味関心のあることを知ることが第一歩だと思います。事業の成功は時間の積み重ねでしかなく、アスリートにとっては練習時間が結果に比例するようなものです。なので飽きずに続けられること、人より苦労と感じずに続けられることが大切だと思います。
 “まずは自分の興味関心のあることを知る”、“人より苦労と感じずに続けられること” がポイントなのですね!
“まずは自分の興味関心のあることを知る”、“人より苦労と感じずに続けられること” がポイントなのですね!
常川さんはご自身でも伝統工芸やコーヒーの事業を創業されていますが、ご自身のビジネスアイディアはどのように決められたのですか?
 最初は「誰かのために」で始めました。伝統工芸士さんたちを支援したかったんですね。でも自分のやりたいこと=支援だという事に気づいたことと、その時の自分には多くの伝統工芸士さんのお役に立つことは難しいと感じたことから、事業自体を学び直しをすることになりました。最初の起業は勢いでしたが、またいつか取り組みたいテーマだと思って温めています。
最初は「誰かのために」で始めました。伝統工芸士さんたちを支援したかったんですね。でも自分のやりたいこと=支援だという事に気づいたことと、その時の自分には多くの伝統工芸士さんのお役に立つことは難しいと感じたことから、事業自体を学び直しをすることになりました。最初の起業は勢いでしたが、またいつか取り組みたいテーマだと思って温めています。

一方でコーヒーの方は自分が好きだからに他ならないものでした。好きなので勉強することも苦にならないし、自分が提供した商品・サービスで人を笑顔にしてお金も頂ける、こんな良いことは無いとあらためて思える事業ですね。
一般化されたビジネスでもあるので、競合も多く大きく売上や利益を伸ばすのは難しいですが、こちらは「飽きずに」続けていける、長く付き合うテーマだと思っています。
特に今はコーヒーが解決するコミュニケーションの課題に着目し、ワーキングスペースやオフィスにバリスタを派遣してコミュニティの醸成に努める事業の芽が出そうです。
 「誰かのために」であったり、「好き」という情熱は、事業を始める時の原動力や継続して続けるための熱い想いは重要ですね。 では常川さんがご自身で事業を開始された当初を振り返ってみて、やって良かったと思う事や、失敗だったと思う事等あれば教えてくださいますか?
「誰かのために」であったり、「好き」という情熱は、事業を始める時の原動力や継続して続けるための熱い想いは重要ですね。 では常川さんがご自身で事業を開始された当初を振り返ってみて、やって良かったと思う事や、失敗だったと思う事等あれば教えてくださいますか?
 振り返ってみて失敗の要素は、「良いサービスを創れば、誰かが買ってくれるはず」と思っていたことです。今は、顧客は発明するものではなく、発見するものだという言葉の整理ができましたが、私もそうでしたが世の中の多くの方が「アイディアを思いついた」という時は、99%が手法(解決手段・リソース)のことを言っていて、ユーザーの話が出てこないことが散見されます。「まずはユーザーを見つけること!」を新しい事業をはじめる多くの方々にあらためてお伝えしています。
振り返ってみて失敗の要素は、「良いサービスを創れば、誰かが買ってくれるはず」と思っていたことです。今は、顧客は発明するものではなく、発見するものだという言葉の整理ができましたが、私もそうでしたが世の中の多くの方が「アイディアを思いついた」という時は、99%が手法(解決手段・リソース)のことを言っていて、ユーザーの話が出てこないことが散見されます。「まずはユーザーを見つけること!」を新しい事業をはじめる多くの方々にあらためてお伝えしています。
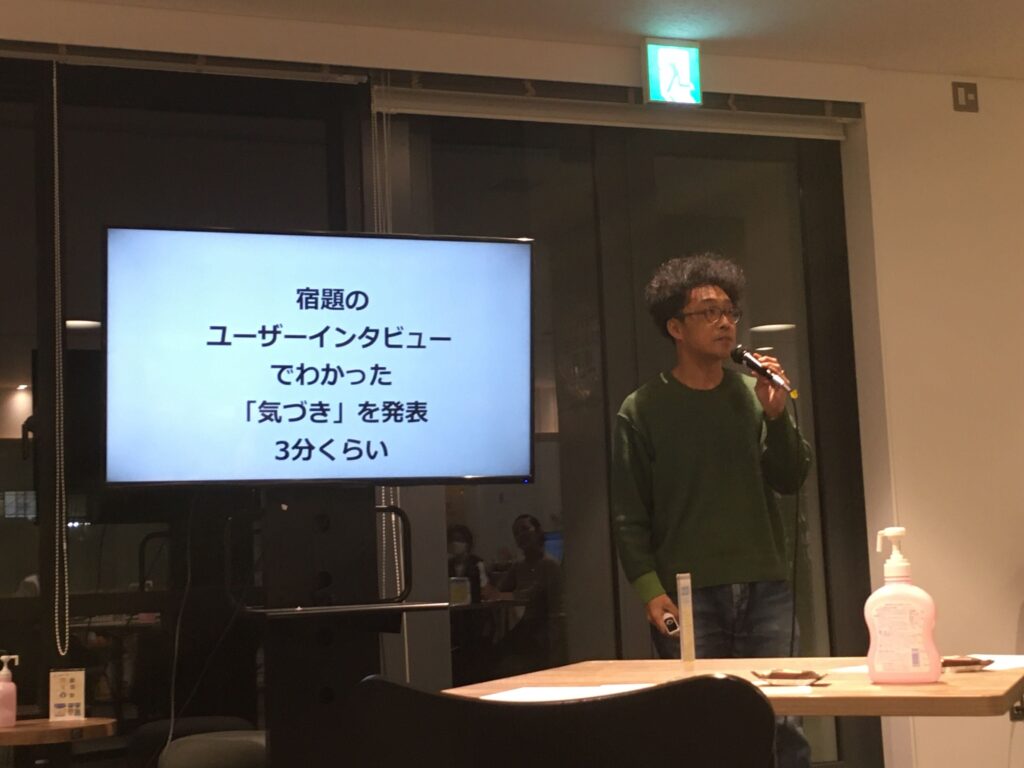
 常川さんはこれまでに様々な分野での事業開発支援のご経験をお持ちですが、特に印象に残っている事業アイディアの開発エピソードなどありますか?
常川さんはこれまでに様々な分野での事業開発支援のご経験をお持ちですが、特に印象に残っている事業アイディアの開発エピソードなどありますか?
 カルビー株式会社のFood for Factoryという、飲食店のポップアップストアが工場にやってくるサービスですね。
カルビー株式会社のFood for Factoryという、飲食店のポップアップストアが工場にやってくるサービスですね。
 お菓子・スナックのカルビーの新しいサービスですね!
お菓子・スナックのカルビーの新しいサービスですね!
 事業開発の初期段階で、担当の方が工場で働く方のために何か新しいサービスをと、泊まり込んで従業員の様子を観察していたことで気付いたのが、工場で働く毎日ではリフレッシュできる瞬間が無いという事実。それをポップアップという非日常的な食の体験を届ける事で解決された事例は、起案した社内起業家の方をそのまま体現するような、優しい事業でした。大きなサービスになって欲しいですね。
事業開発の初期段階で、担当の方が工場で働く方のために何か新しいサービスをと、泊まり込んで従業員の様子を観察していたことで気付いたのが、工場で働く毎日ではリフレッシュできる瞬間が無いという事実。それをポップアップという非日常的な食の体験を届ける事で解決された事例は、起案した社内起業家の方をそのまま体現するような、優しい事業でした。大きなサービスになって欲しいですね。
 工場で働く方に食品を届ける方法は様々あるけれど、お腹を満たす事にプラスアルファの価値、“リフレッシュ”も提供する、食品メーカーの新規事業の事例ですね。興味深いです!ありがとうございます。
工場で働く方に食品を届ける方法は様々あるけれど、お腹を満たす事にプラスアルファの価値、“リフレッシュ”も提供する、食品メーカーの新規事業の事例ですね。興味深いです!ありがとうございます。
常川さんが考える、どのような分野の事業にも共通する、新しいビジネスの初めの一歩、或いはここから始めるべき!というスタートライン等、あれば教えていただけますか?
 先ほどお伝えしましたが、「自分の興味関心のあることを知ること」が第一歩だと思います。
先ほどお伝えしましたが、「自分の興味関心のあることを知ること」が第一歩だと思います。
まずは自分を知ること、次いで事業を知ること、そしてユーザーを知る努力をし続けることが事業の本質だと思います。
 「自分を知る」 がまず基本なのですね。 次にビジネスアイディアの「育て方」についてお聞きしたいのですが、やりたいビジネスアイディアが見つかった後、それを育て成長させる為に、大切な事はどんなことですか?
「自分を知る」 がまず基本なのですね。 次にビジネスアイディアの「育て方」についてお聞きしたいのですが、やりたいビジネスアイディアが見つかった後、それを育て成長させる為に、大切な事はどんなことですか?
 事業を創るのに「グロースハック」という言葉はありません。日々の積み重ねがユーザーを増やし、ひいては売上をつくります。答えは自分とユーザーの中にあると信じて、事業と向き合うことが大切だと思います。
事業を創るのに「グロースハック」という言葉はありません。日々の積み重ねがユーザーを増やし、ひいては売上をつくります。答えは自分とユーザーの中にあると信じて、事業と向き合うことが大切だと思います。

 日々の積み重ね・・、はやり事業も毎日コツコツが基本ですね。次に”地域性を活かすビジネス“という視点からお聞きしたいのですが、「地域性をどうビジネスに活かして良いかわからない…」、という方に、地域性をビジネスに活かすヒントやアドバイスお願いできますか?
日々の積み重ね・・、はやり事業も毎日コツコツが基本ですね。次に”地域性を活かすビジネス“という視点からお聞きしたいのですが、「地域性をどうビジネスに活かして良いかわからない…」、という方に、地域性をビジネスに活かすヒントやアドバイスお願いできますか?
 地域の課題というキーワードは良く出てきますが、その地域や地域性という言葉自体が解像度が荒いものです。
地域の課題というキーワードは良く出てきますが、その地域や地域性という言葉自体が解像度が荒いものです。
なので、もっと掘り下げていくことで、差異や特徴、定量的な違いがわかり、特に他の地域と比較してみないと本当の「地域性」は見つけにくい(特に住んでいる人だからこそ)部分があると思います。
 確かに・・・、 “地域の課題”だけだと相当ぼやっとしていますね。 その地域の課題が他の地域と比較してどうなのか?という視点で一歩明確に見えてきそうです。
確かに・・・、 “地域の課題”だけだと相当ぼやっとしていますね。 その地域の課題が他の地域と比較してどうなのか?という視点で一歩明確に見えてきそうです。
常川さんには 毎年秋にMegribaで開催する連続セミナーの講師として、山口市に何度か来ていただいていますが、山口の特性や、他の地域と比べて感じる事などありますか?
 似ている都市で言うと、岡山や三重、私の地元の栃木県もですが、一定の社会的な豊かさがある地域だと感じました。豊かであることで、教育や福祉といった部分や、地域で困ってる方をベースにしたアイディアが出やすいと思いました。
似ている都市で言うと、岡山や三重、私の地元の栃木県もですが、一定の社会的な豊かさがある地域だと感じました。豊かであることで、教育や福祉といった部分や、地域で困ってる方をベースにしたアイディアが出やすいと思いました。
 Megribaでも教育や福祉の分野での起業に興味を持たれる方は多いです。自分の身の回り、地域で困っている方を探してみるのもヒントになりそうです。ありがとうございます。
Megribaでも教育や福祉の分野での起業に興味を持たれる方は多いです。自分の身の回り、地域で困っている方を探してみるのもヒントになりそうです。ありがとうございます。

 最後に、常川さんが考える新規事業のアイディアを見つけ、育てる醍醐味はどんな事だと思いますか?
最後に、常川さんが考える新規事業のアイディアを見つけ、育てる醍醐味はどんな事だと思いますか?
 事業を創るということは、正解の無い中にいかに自分なりの正解を見出すかというところに、難しくも楽しい部分を感じられるかどうかだと思います。正解がひとつで、それをやれば良いんだ、という考え方もありますが、不確かな状況を楽しめるような、冒険家タイプの方が一生に一度は挑戦して見ても良いと個人的には思います。ただ、大きな失敗をすると立ち直れなくなるので、小さく早く失敗できるように、また色々な方に甘えて助けてもらえるような起業の仕方を心がけると良いと思います。
事業を創るということは、正解の無い中にいかに自分なりの正解を見出すかというところに、難しくも楽しい部分を感じられるかどうかだと思います。正解がひとつで、それをやれば良いんだ、という考え方もありますが、不確かな状況を楽しめるような、冒険家タイプの方が一生に一度は挑戦して見ても良いと個人的には思います。ただ、大きな失敗をすると立ち直れなくなるので、小さく早く失敗できるように、また色々な方に甘えて助けてもらえるような起業の仕方を心がけると良いと思います。
 小さく失敗しながら、甘えて助けて(支援して)もらいながらですね!ぜひ山口の皆さんにはMegribaの支援メニューも活用いただければと思います。常川さん、本日は貴重なお話ありがとうございました。9月の連続講座も楽しみにしています!
小さく失敗しながら、甘えて助けて(支援して)もらいながらですね!ぜひ山口の皆さんにはMegribaの支援メニューも活用いただければと思います。常川さん、本日は貴重なお話ありがとうございました。9月の連続講座も楽しみにしています!
【インタビュアー:黒澤直子(Megribaインキュベーションマネージャー)】
編集後記:にこやかで丁寧にお話しされる常川さんの”どんな事業も最初はひとりのユーザーから始まっています。まず一人目のユーザーを探しましょう!” という言葉が印象的なインタビューでした。常川さんの講義が受けたい、相談したい!という方おすすめです。↓

<<お知らせ>> 毎年秋にMegribaで開催している、常川氏講師の“Megriba Startup Camp” (連続5回講座、定員20名)は今年も9月から開催予定です。事業のアイディアを見つけたい方や、始めた事業を成長させたい方に特におススメです。
また、常川氏に個別で相談できる「新規事業アイディア相談会」も申込受付中。起業したいけど事業アイディアが固まらないか方、企業の新規事業を担当される方にもおススメです。


常川朋之氏 (株式会社エンターテイン 代表取締役)
商工会議所職員として企業支援や総務職を経験。15年に伝統工芸を活用した事業で起業するも失敗。
16年にアクセラレーターへ参画。特に地方行政が主催するプログラムを企画・運営し、東京都内・仙台市・愛知県・大阪府の起業家支援プロジェクトなどでディレクションとメンターを担当し、地域のスタートアップ等を支援。
19年4月に改めて法人を設立、20年度から大手企業の新規事業創出に関わるプロジェクトをハンズオン支援。直近ではスタートアップ支援の社団法人を設立し理事に就任。自らも起業家としてコーヒー事業を展開している。



